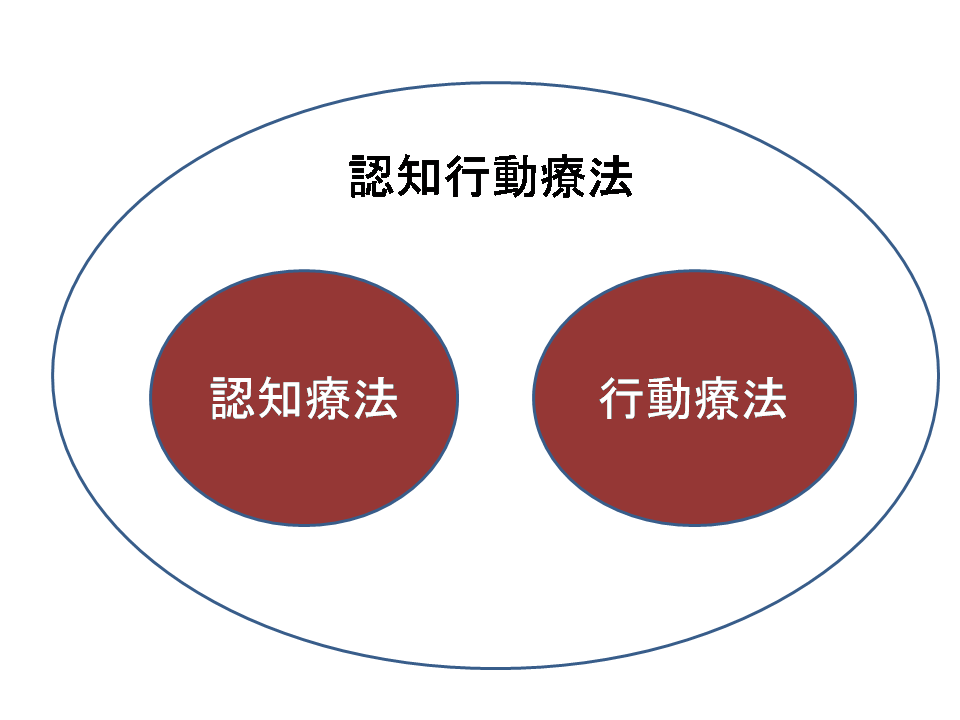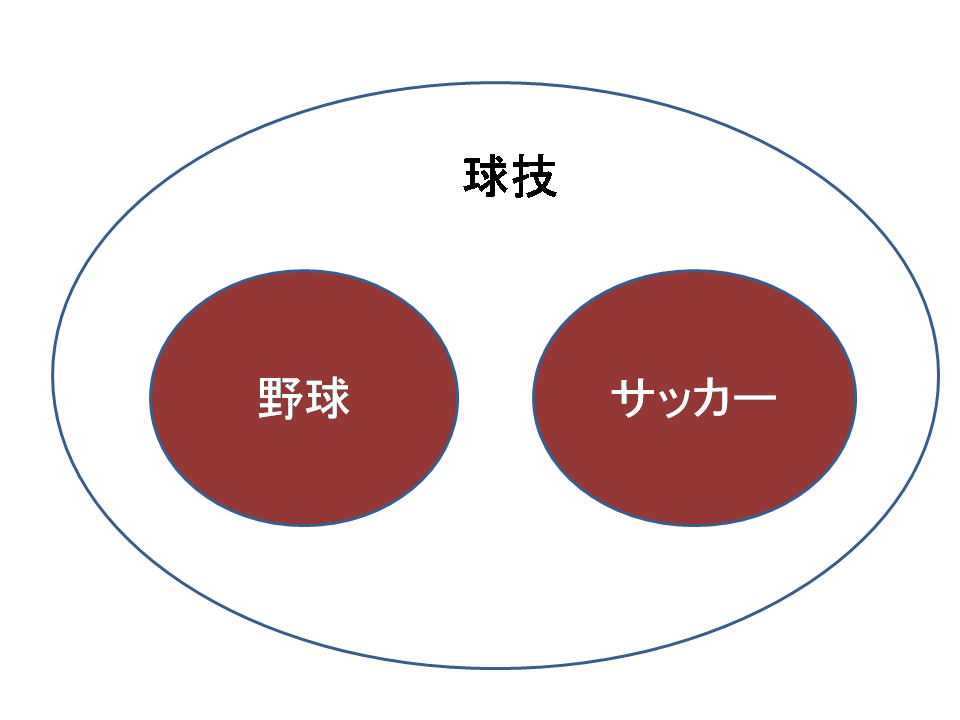浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
メンタルを強くしたい。
そのためには心理学や自己啓発本を読む。
このパターンにはまっている人はだいたいうまくいかないものです。
読むとちょっと元気になれるかもしれません。
しかし、現実に直面するとすぐに元に戻ります。
栄養ドリンクみたいなもんですかね。
そんな人が参考にされるとよい言葉を患者さんから聞きました。
「メンタルは強くならないって思ったら楽になりました」って。
うん?ようわからん。
メンタル強くならなかったら今のままで苦しいじゃないか!って思ったあなた。
そこが落とし穴なんですよ。
メンタル強くするなんて無駄なこと
「メンタルを強くする」ってどんなイメージですか?
「嫌な人から何言われても流せるようなりたい」
「ネガティブ思考をポジティブにしたい」
「落ち込まない強靭な精神力になりたい」
って思いがち。
いわゆる「精神的マッチョ」をイメージしていません?
それは無理です。
そんな方法があったら私が知りたい。
今頃自己啓発セミナーを開くか、宗教家になってます。
誤解している人が多いのですが、認知行動療法やったってポジティブ思考とか精神的マッチョになれるわけないですよー!
本のタイトルにだまされてはいけません。
メンタル強くしたいって人は自己否定してるんです。
「きついことを言われるとすぐに気にしてしまう自分はダメなんだ」
「ネガティブな自分はダメなんだ」
「落ち込みやすい自分はダメなんだ」って。
メンタルを強くなんて思っているうちは自己否定しているだけ。
本当は弱いところを受け入れる「強さ」が必要なんですよ。
「メンタル弱いですけど、何か問題でも?」って人の方が強そうに思いません?
嫌なことがあると、クヨクヨして、ネガティブになり、落ち込むことはある。
それでもまぁなんとかやれる。
どうしようもないところは、うまくストレスから距離をとりながらやっていく。
それができればいいんですよ。
ソコソコってやつです。
これができると気持ちが楽になります。
精神的なマッチョなんて目指すだけ無駄。
むしろ精神を悪化させるんじゃないですかね。
うつと不安のカウンセリング・認知行動療法ご希望の方は浦和すずのきクリニックの受付、 または電話048-845-5566で「カウンセリングの予約」をして下さい。
他の病院に通院中の方、どこにも通院されていない方でもカウンセリングは受けられます。