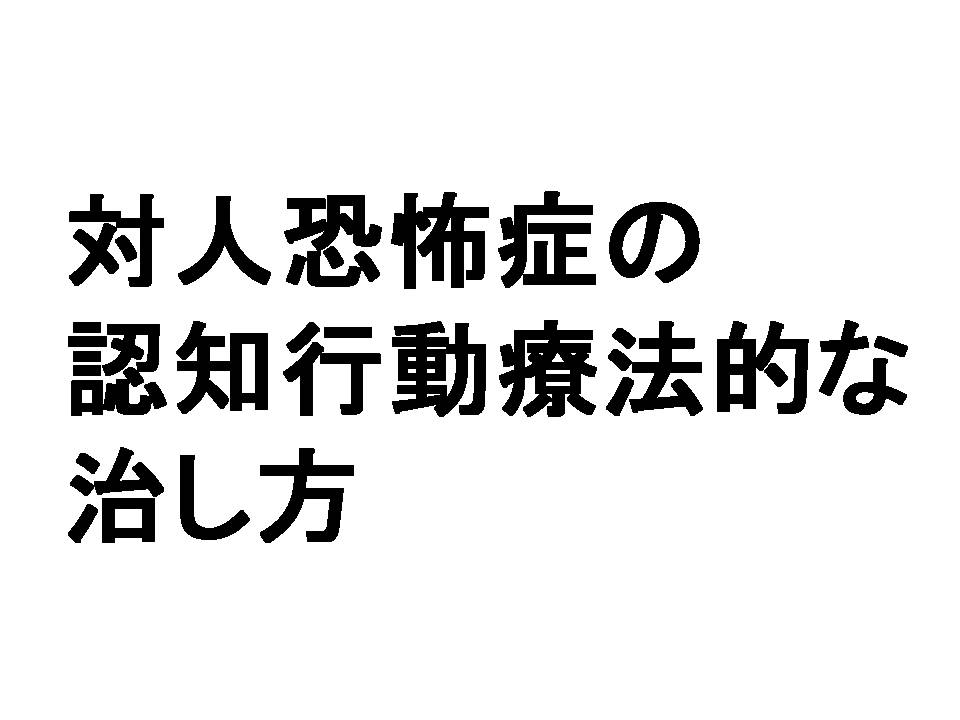
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
さいたま市主催で一般の方向け対人恐怖症の学習会やります!
講師は私です。参加無料、申し込み不要ですよー。
浦和パルコに入っている施設でやるんで、買い物ついでに聞いていってください。
ただし先着100名です。
今月のさいたま市報にも載っていますが、全く説明が書かれていないので補足しておきます。
詳細はこちら!
埼玉県さいたま市にある浦和すずのきクリニック(精神科・心療内科)のカウンセラー(臨床心理士)がうつ病、パニック障害、社会不安障害、強迫性障害、摂食障害(過食症)、認知行動療法の情報と日々の活動を書きます
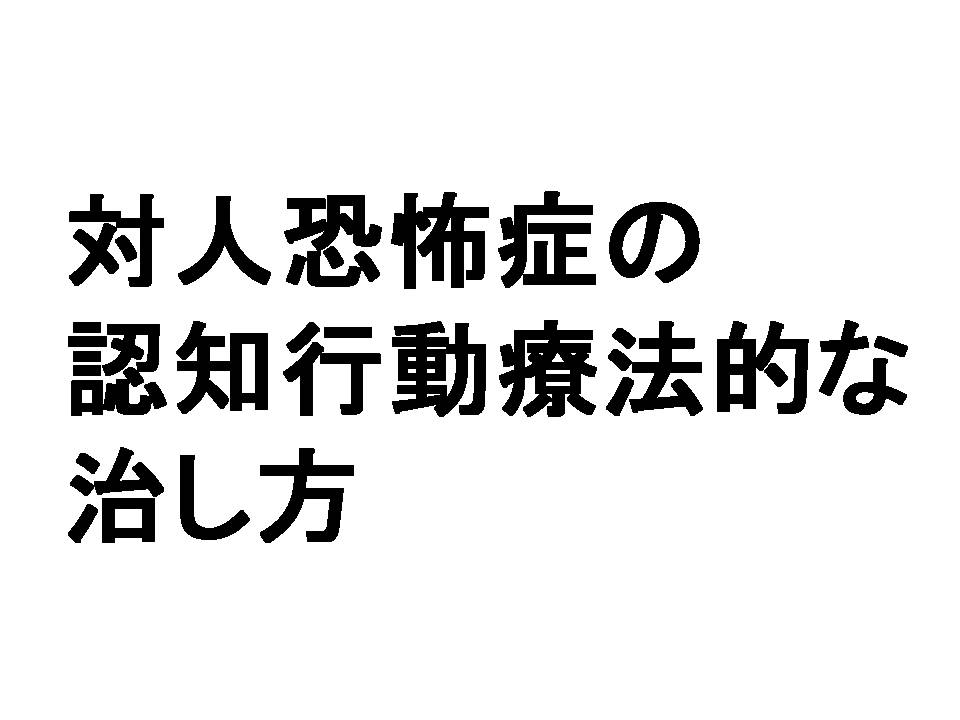
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
さいたま市主催で一般の方向け対人恐怖症の学習会やります!
講師は私です。参加無料、申し込み不要ですよー。
浦和パルコに入っている施設でやるんで、買い物ついでに聞いていってください。
ただし先着100名です。
今月のさいたま市報にも載っていますが、全く説明が書かれていないので補足しておきます。
詳細はこちら!

浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
人前で緊張して、震えてしまう、赤面してしまう、「否定的に思われているのでは」と考えてしまう。
そんな人がよくあるパターンとして「緊張しない努力」をしています。
リラックスしようとしたり、薬等を飲んで安心しようとしたり。
ネットで「緊張しない方法」を調べていませんか?
しかし、多くの人がそのようなことをしても、緊張感から逃れられず苦しんでいます。
その理由の一つが緊張に対しての考え方。
緊張で困る人は「緊張しない方法」を求めています。
実はこれが悪化要因となっているのです。
この記事では人前での緊張で困っている人は、どんな考え方がまずくて、緊張に対してどう向き合っていけてばよいのかについて説明していきます。
読んですぐに実践できる方法です。
緊張に対しての扱い方がわかることで、悩みから解放される一歩となるでしょう。

浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
春の時期になると増える相談事の一つは、人前で話す時の緊張についてです。
自己紹介とか大勢の前で話すのが苦手な人多いんですよね。
よくあるのはPTAの役員になったり、仕事で異動となったりして、人前で話す機会が増えたとか。
話すことが苦手な人は、苦手なことを悪化させる行動や考え方をしています。
これを知っているか、知っていないかで大きな差が出るのです。
今回の記事では、人前で話すのが苦手な人が克服するために知っておきたい7つのポイントを紹介します。
実践していくことで、以前よりマシになってきますよ。
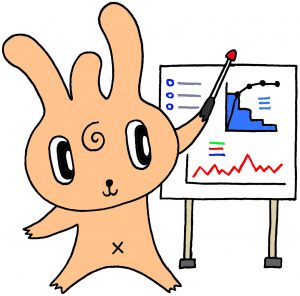
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
会議、司会、プレゼン、自己紹介など、人前で話すのが苦手な人は多いです。
対人恐怖症や社交不安障害の人は特に困りますよね。
私も人前で話すのは苦手な方です。
それでも大勢の前で話す機会が時々あります。
先日、専門家向けの研修会に講師として行きました。
何度やっても緊張します。
内心「今日の研修会つまらないと思われたらどうしよう」とどっかで思っているし、時々何を話しているかわからなることもあります。
ちょっと震えたりすることも。
しかし、周囲からみると堂々と自信ありげに話していると見られます。
だから私が「人前で話すのは緊張する」と言っても誰も信じてくれません。
「心臓に毛が生えてそう」ってばかりいわれます。
なぜ、そのような私の内面的な評価と外の人の評価が違うか?
他人は話す時の見え方、聞いているモノで判断していて、中身はわからないってことなんです。
この記事ではどうすれば、話している時に堂々としているようにみられるのか?
4つのポイントについてご紹介します。
実践すれば話すことに自信がなくても、フツウ程度に見えるようになります。
話すのが苦手な人とは逆のことをやるので、病的に困っている人にも有効です。
悩んでいる人は練習してみましょう。
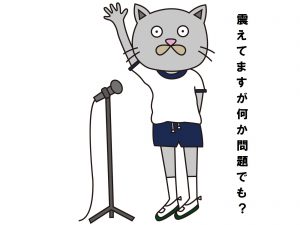
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
人前で緊張して震えてしまう。
スピーチをする時、申込書を書く時、お酌をする時、作業をする時に震えて困っている。
そんな人はどうすればこの問題を解決できるのか?
今回は人前で緊張して震えてしまう人の対処法について紹介します。
研究で効果が認められている方法の一部ですで、お困りの方は実践してください。

浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
社交不安症・障害という病気をご存知ですか?
人前で緊張して生活に支障が出ている人に当てはまることがあります。
対人恐怖症、あがり症、赤面症、とかいろいろ呼び名がありますが、名前としては社交(社会)不安障害(症)と呼ぶことが多くなりました。
10代の頃から悩んでいる人も多いのですが、ほっとくと大人になって生活に支障をきたすようになります。
「恥ずかしがり屋の性格」と思っていても、社交不安障害かもしれません。
そうだとしたら、早めに気づいて治療すると生活がとっても楽になります。
今回は社交不安障害の代表的な症状について紹介します。
仮に病気じゃなくても困っているならば、治療を受けることをおすすめします。
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
人前に出たり、人前で話したり書いたりすることが不安。
あがり症の人はずっと悩んでいます。
ネットではいろんな克服方法が挙げられていますが、それほど効果を感じられないと思う人も多いでしょう。
それもそのはず。
ほとんどのものが効果が認められていないので。
まして、話し方教室にいっても治るハズもなく。
あがり症は病名ではありません。
病名に近いものとして「社交不安障害」があります。
社交不安障害には認知行動療法という方法が効果が認められています。
あがり症であろうが社交不安障害であろうが、治し方は変わりません。
今回は、あがり症の基本的な克服方法について説明します。
薬以外の方法で何とかしたい!って人は必見です。
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
人前で顔が赤くなることを恥ずかしく思う赤面症の人は日本人に多いです。
社交不安障害の代表的な症状の一つ。
10代の頃から気にしている人も珍しくはありません。
治療法は薬か認知行動療法が有効とされています。
薬を飲んでも一時的な効果であったり効果がなかったりする場合は、認知行動療法がおすすめです。
というか、それくらいしか有効な対処方法はないです。
催眠とか過去を探るとかリラクゼーションとか漢方とか、科学的根拠はないですよ。
では、赤面症(赤面恐怖症)にはどう対応していったらよいのか?
今回は赤面症によくある3つの考え方のクセを変えることで克服していく方法についてご紹介します。
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
対人恐怖症の人が仕事をするときに困りそうなことがあります。
・電話している時に誰かに聞かれる不安
・人が自分のことを「変だ」とみていたり、自分の表情が不快にさせているという不安
・会議などで発表するときの不安
これらの3つの不安について、どうすればよいのか?
これまでの過去記事にリンクしておきましたので、困っている方は復習してみてください。
電話がかかってきたときに、その内容を聞かれて「間違ったことをいっているのではないか」と不安になります。
電話をとらないようにしているとか、逃げているとずっと不安なままですよー。
対処法はこちら
同僚が自分のことを「変な奴」と思ってみているのではないかと不安なります。
また自分が相手に不快感を与えていると思っている人もいます。
どっちも自分の考え方のクセなのですが、理屈で説明してもだいたいダメです。
いろいろ実体験することが必要ですね。
特に人目を気にする人は、人を見ていないってことに注意しましょう。
対処法はこちら
どれくらい人は他人のことを見ているのか?コンビニで実験してみました
会議で発言するときに、声や体が震えるのが怖くなります。
リラックス法を学んでも無駄です。
会議の前に薬飲んでごまかしていても、治るわけでもないですよね。
きちんと対処法を練習しておきましょう。
対処法はこちら
自己紹介で緊張する人が克服するために知っておきたい7つのコト
うつと不安のカウンセリング・認知行動療法ご希望の方は浦和すずのきクリニックの受付、 または電話048-845-5566で「カウンセリングの予約」をして下さい。
他の病院に通院中の方、どこにも通院されていない方でもカウンセリングは受けられます。
浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
対人恐怖症・社交不安障害の人は、他人から「どう思われるか」「ドキドキ」とか自分の考えや体の感覚に注意が向いています。
今やっていることに注意が向かないのです。
考えや体の感覚に注意が向くとどんどん不安が強くなります。
緊張をなんとかしようとして、今何やっているかわからなくなった経験ありません?
対策として外に注意を向けていく練習をしていくとよいのは以前の記事で書きました。
今回はこの練習の続きについて書いていきます。
記事では見えたものに注意を向けるよう書きました。
ある程度見えているものに注意が向けられるようになりましたか?
今度は不安な場面をイメージしてください。
発表している場面とか。
「変に思われたらどうしよう」「動悸がしてきた」など自分に注意を向けます。
不安な感覚でいっぱいになるくらいに。
不安な感覚になったらもう一度外に(見えているものに)注意を向けましょう。
いきなり注意を方向を変えることは難しいかもしれませんが、やってみましょう。
外に注意が向けられたら、また不安なことを考えましょう。
注意を外に向ける
→不安にさせて注意を自分に向ける
→注意を外に向ける
→注意を自分に向ける
これを繰り返します。
この練習方法をしていくと、不安場面で外に注意を向けやすくなり、今やっていることに注意が向きやすくなります。
不安なくなるというよりは、不安でもそれが頭の中いっぱいになるのではなく、今やるべきことに注意を割けるようになるって感じでしょうか。
出来るだけ毎日練習しましょう。
ちょっとやっただけではあまり役に立ちません。
うまく行かない時は相談しに来てくださいね。
うつと不安のカウンセリング・認知行動療法ご希望の方は浦和すずのきクリニックの受付、 または電話048-845-5566で「カウンセリングの予約」をして下さい。
他の病院に通院中の方、どこにも通院されていない方でもカウンセリングは受けられます。